MuseScoreのある優れた挙動を利用すると、音符間隔を個別に調整せずとも、音符間隔を無調整で揃えることができます。第三回ではこの方法を紹介したいと思います。
諸悪の根源は伸縮する小節幅
 |
| この音符間隔が小節ではなく段基準で実現できるべきである |
段を一つの小節で構成する「一段一小節法」
段を単一の小節で構成し、それを本来の小節数に縦線で分割することで、音符間隔はデフォルトで揃います。これによって段の中の音符間隔の挙動を、小節の中の音符間隔の挙動と同じにするのです。

この手法では、楽譜入力したファイルとは別に浄書用に新規にファイルを作ることをお勧めします。まず、浄書用のファイルで、右図のように1小節ずつ「譜表の折り返し」を挿入しておきます。
 1段に4/4拍子を4小節入れる場合、小節の実際の拍数を16拍に設定します。MuseScoreの小節は、「小節プロパティ」で拍子記号とは異なる拍数にすることができます。「小節プロパティ」の「小節の長さ」の「実際」の値は、浄書する楽譜の1段の拍数に設定します。
1段に4/4拍子を4小節入れる場合、小節の実際の拍数を16拍に設定します。MuseScoreの小節は、「小節プロパティ」で拍子記号とは異なる拍数にすることができます。「小節プロパティ」の「小節の長さ」の「実際」の値は、浄書する楽譜の1段の拍数に設定します。一段分の拍数に設定して一段分の音符を入力したら (*) 、4/4拍子であればパレットから縦線を4拍ずつ挿入していきます。
*浄書用のファイルで、全ての段で小節の拍数を段の拍数に設定したら、元のファイルから音符をコピーペーストすると楽です。

この手法では、1段が1小節として処理されているので、小節番号がずれます。従って小節のプロパティで小節番号を手動で調節する必要があります。このことからも、楽譜入力時のファイルとは別に浄書用にファイルを作成し、楽譜入力時のファイルで小節番号を参考にしつつ、浄書用ファイルで「小節のプロパティ」から「小節番号の増減」で手動で合わせると良いでしょう。
この時の割振りの挙動を見よ
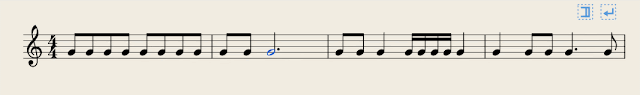 |
| デフォルトで割振り(後の間隔)の挙動 |
 |
| 段を単一の小節で構成した時の割振り(後の間隔)の挙動 |
※「割振り」のある程度の数値までは、音符間隔が変化しませんが、その数値を超えると個別の音符間隔が伸縮します。「割振り」はあくまで「加算されたスペース」の増減の機能なので、素の音符間隔を狭めることはできません。
注意すべき点
・常に同一小節内と判定されるので、必要な臨時記号が抜けます。
・全休符は通常小節の中央に配置されますが、この手法では段で一つの小節と処理されるので、拍に合ってしまいます。手で中央に合わせる必要があります。
・声部が複数あるときに符尾の上下に注意してください。同一小節で処理されるため、複数の声部があると、声部1が常に上向きになります。
「一段一小節法」の限界
この手法はMuseScoreの小節の概念を否定するものです。したがって、小節に依存する機能が含まれる部分には使えません。MuseScore2では拍子記号、調号、リピート線は小節に依存するために、それらが途中に含まれる段ではこの手法は使えません。
・拍子記号
MuseScore2,3共に、拍子記号は小節の途中に挿入できません。拍子記号と小節は密接に関連があるので浄書ソフトとしては当然でしょう。したがって段の途中で拍子記号が変わるような部分にはこの手法は使えません。
・調号
MuseScore2では調号を小節の途中に挿入できないため、転調する箇所が含まれる段には、この手法は使えません。ただし、MuseScore3では小節の途中の拍で調号を挿入できるので、この手法は使えます。
・リピート線
 MuseScore2ではリピート線を小節の途中に挿入することができません。したがって複数の譜表を含む楽譜ではこの手法は使えません。ただし単譜表の楽譜であれば、小節途中に挿入した縦線をインスペクタでリピート線に変更できるため、リピート線を含む譜例でもこの手法が使えます。
MuseScore2ではリピート線を小節の途中に挿入することができません。したがって複数の譜表を含む楽譜ではこの手法は使えません。ただし単譜表の楽譜であれば、小節途中に挿入した縦線をインスペクタでリピート線に変更できるため、リピート線を含む譜例でもこの手法が使えます。MuseScore3ではリピート線や様々な小節線を、パレットから小節の途中の拍に挿入できるので、この手法を使うことができます。ただ、なぜかMuseScore3は小節途中に挿入した小節線をインスペクタで種類を変えることができないようです。
 このように段全体を単一の小節にできない場合でも、部分的に複数の小節を単一の小節でまとめることで、音符間隔を揃えるための作業を多少減らすことができます。右の譜例では単一の小節で表現した右側3小節に合わせて左側2小節を、第二回での機能を使って手動で調節すると良いでしょう。
このように段全体を単一の小節にできない場合でも、部分的に複数の小節を単一の小節でまとめることで、音符間隔を揃えるための作業を多少減らすことができます。右の譜例では単一の小節で表現した右側3小節に合わせて左側2小節を、第二回での機能を使って手動で調節すると良いでしょう。さて次回はMuseScore3におけるこの手法の効果について書きたいと思っています。お楽しみに。










0 件のコメント:
コメントを投稿